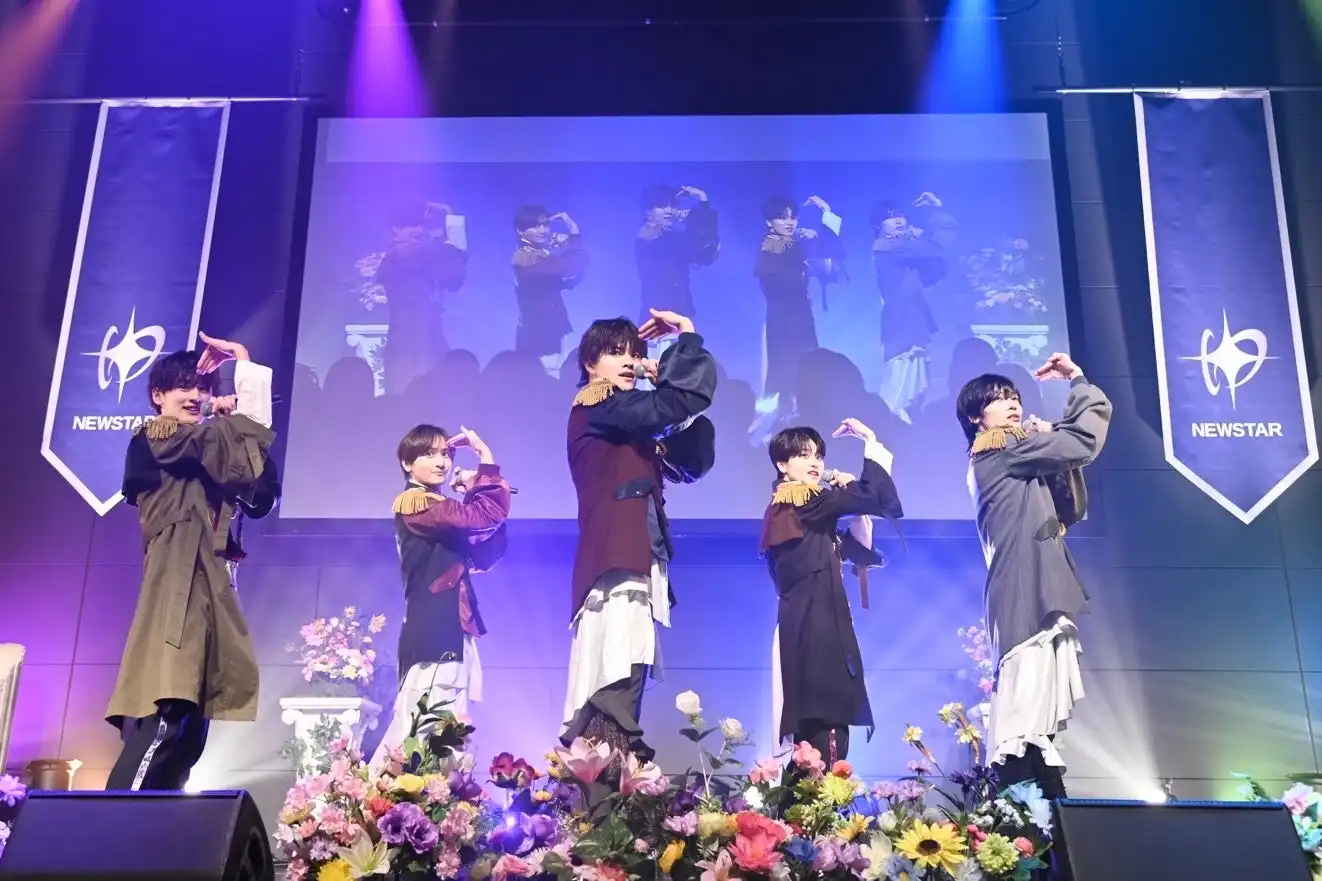LVMとは
LVM(Logical Volume Manager)は、LinuxなどのOSで利用できるストレージ管理の仕組みです。物理的なストレージを抽象化し、柔軟なボリューム管理を実現します。LVMを使用することで、ストレージの拡張や縮小、スナップショットの作成などが容易になります。
従来のストレージ管理では、パーティション分割された物理ディスクを直接ファイルシステムとして利用していました。しかし、LVMでは、物理ボリューム(PV)、ボリュームグループ(VG)、論理ボリューム(LV)という3つの概念を導入することで、より柔軟な管理を可能にしています。これにより、システム管理者は物理的な制約にとらわれず、論理的な視点からストレージを管理できます。
LVMは、サーバーの運用において、ダウンタイムを最小限に抑えながらストレージ容量を拡張する必要がある場合などに特に有効です。また、データのバックアップやテスト環境の構築においても、スナップショット機能を活用することで、効率的な運用を実現できます。LVMを理解し活用することで、ストレージ管理の効率化と柔軟性の向上が期待できます。
LVMの構成要素
「LVMの構成要素」に関して、以下を解説していきます。
- 物理ボリューム(PV)
- ボリュームグループ(VG)
物理ボリューム(PV)
物理ボリュームは、LVMにおける最も基本的な構成要素であり、物理的なストレージデバイス(ハードディスクやSSDなど)をLVMが管理できる状態にしたものです。具体的には、ディスク全体またはパーティションをPVとして初期化することで、LVMの管理下に置きます。PVは、ボリュームグループ(VG)を構成するための基礎となります。
PVを作成する際には、pvcreateコマンドを使用します。このコマンドを実行することで、指定したデバイスにLVMに必要なメタデータが書き込まれ、PVとして認識されるようになります。PVはVGに組み込まれることで、論理ボリューム(LV)の作成に使用できるようになります。
| 要素 | 説明 | コマンド |
|---|---|---|
| 物理デバイス | HDDやSSDなど | /dev/sda1 |
| 初期化 | LVM管理下に置く | pvcreate |
| メタデータ | LVMに必要な情報 | LVM管理領域 |
| VGへの組み込み | LV作成に使用 | /dev/sda1 |
ボリュームグループ(VG)
ボリュームグループは、一つまたは複数の物理ボリューム(PV)をまとめたもので、論理ボリューム(LV)を作成するためのリソースプールとして機能します。VGは、PVを抽象化し、LVに対して連続したストレージ領域を提供します。VGを作成することで、複数の物理ディスクを一つの大きなストレージとして扱うことが可能になります。
VGを作成する際には、vgcreateコマンドを使用します。このコマンドにPVを指定することで、VGが作成されます。VGの容量は、VGに組み込まれたPVの合計容量となります。LVは、このVGから必要な容量を割り当てることで作成されます。
| 要素 | 説明 | コマンド |
|---|---|---|
| PVの集合体 | HDDやSSDなど | vgcreate |
| リソースプール | LVM管理下に置く | pvcreate |
| 容量 | LVMに必要な情報 | LVM管理領域 |
| LVの割り当て | LV作成に使用 | vgcreate |