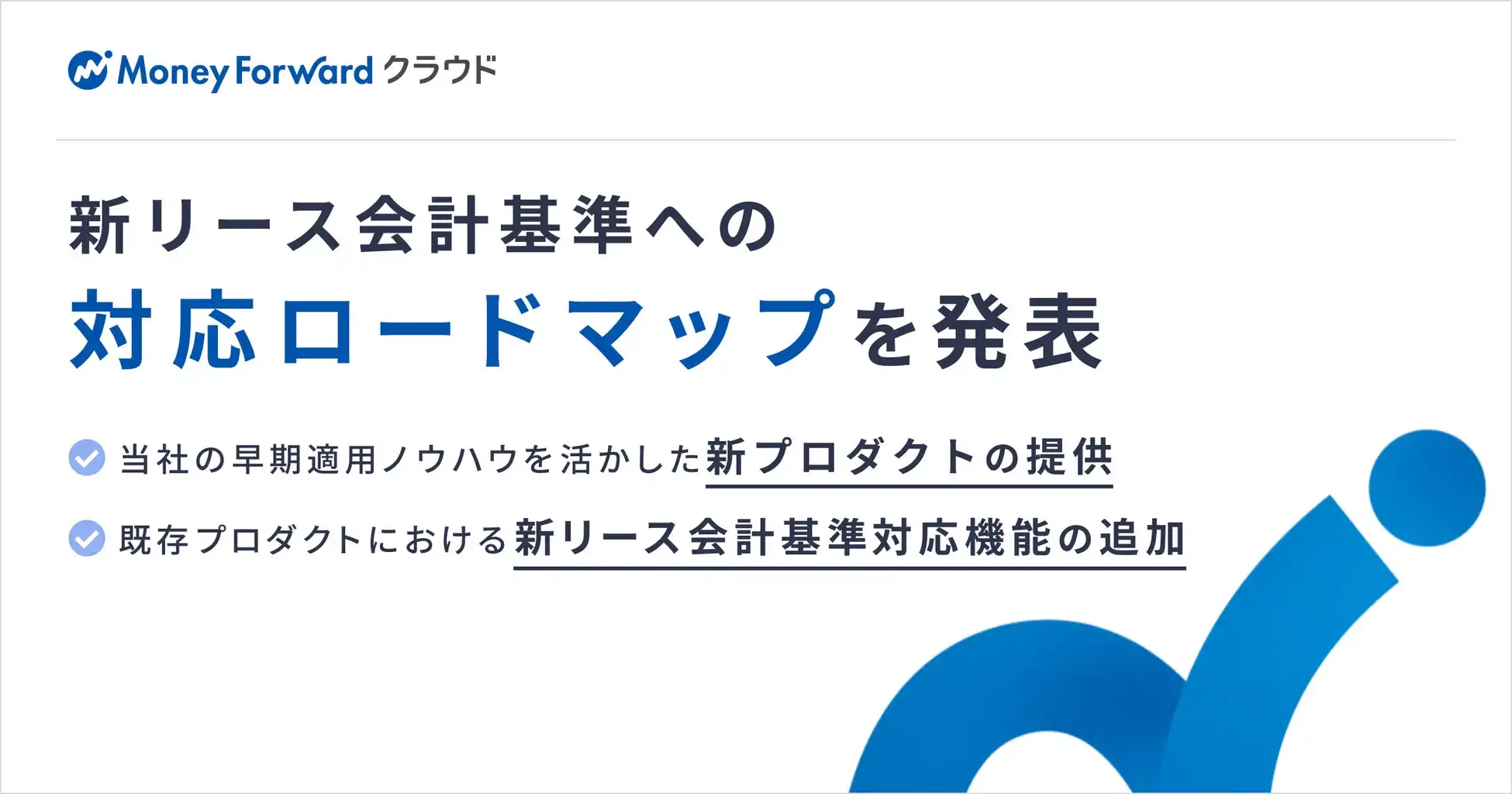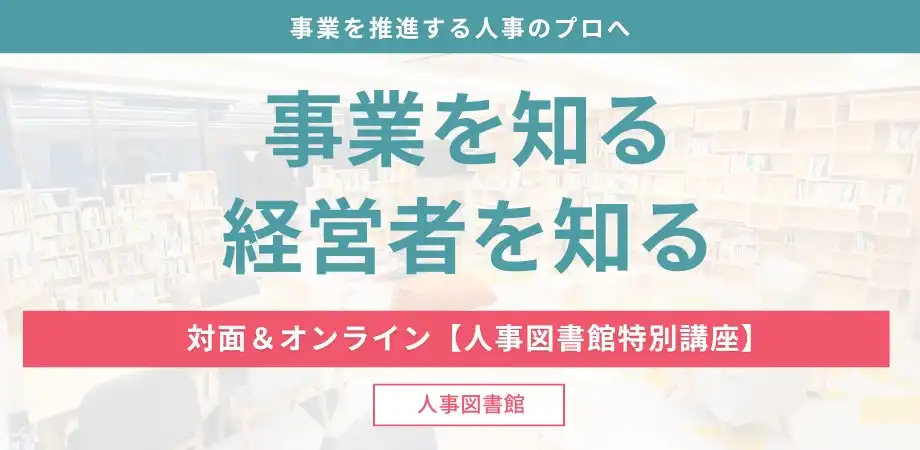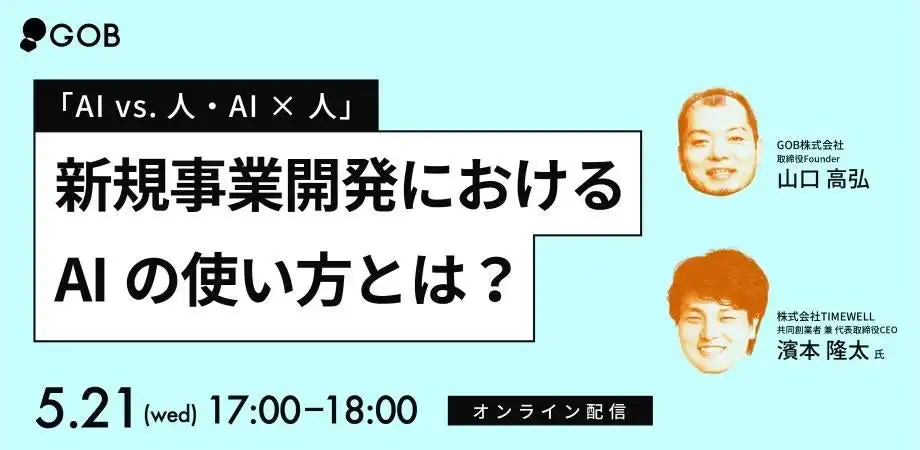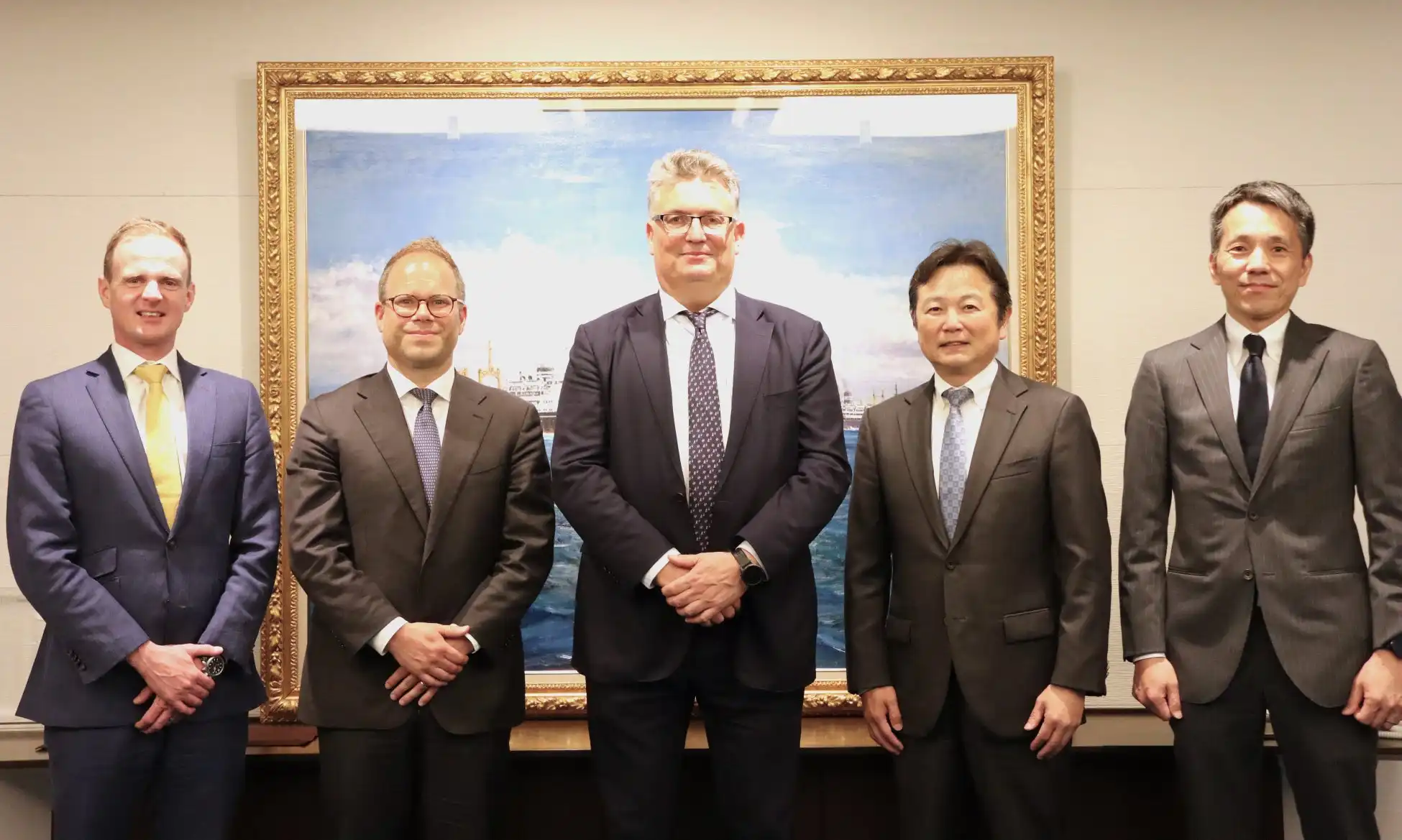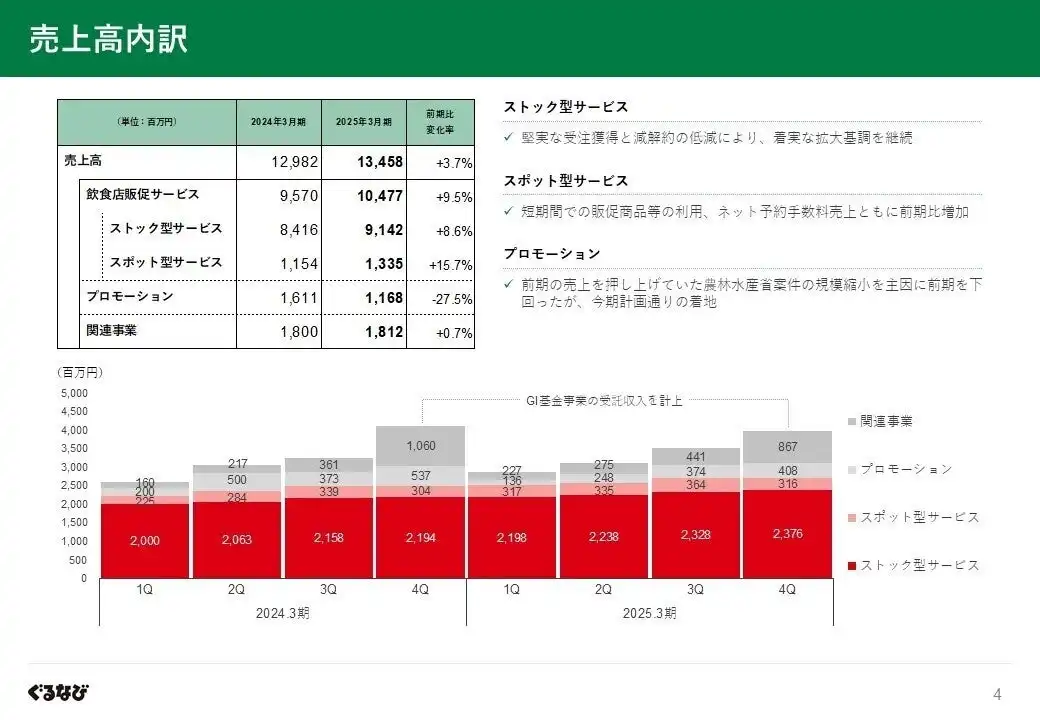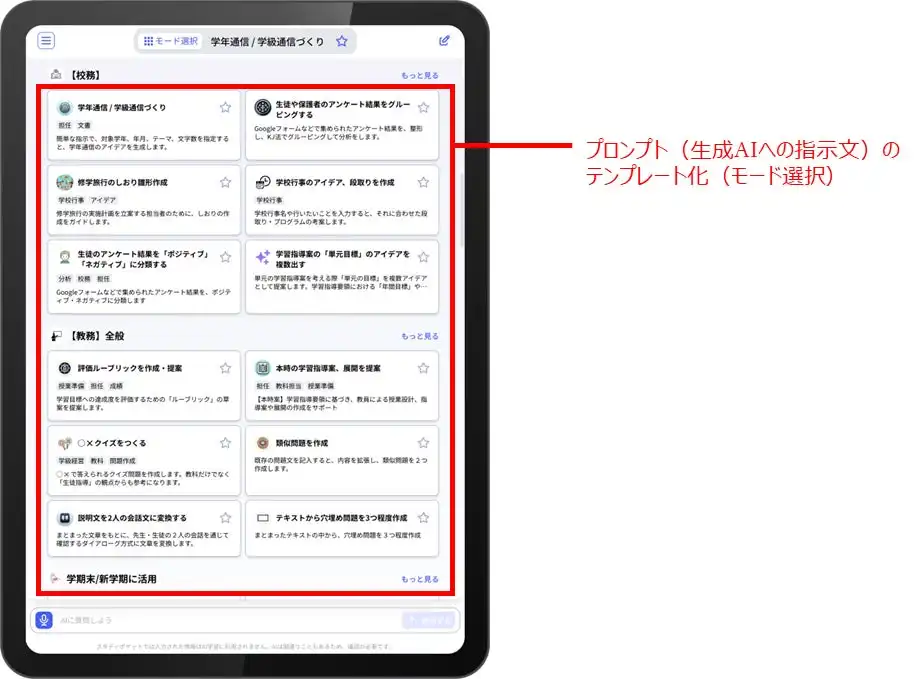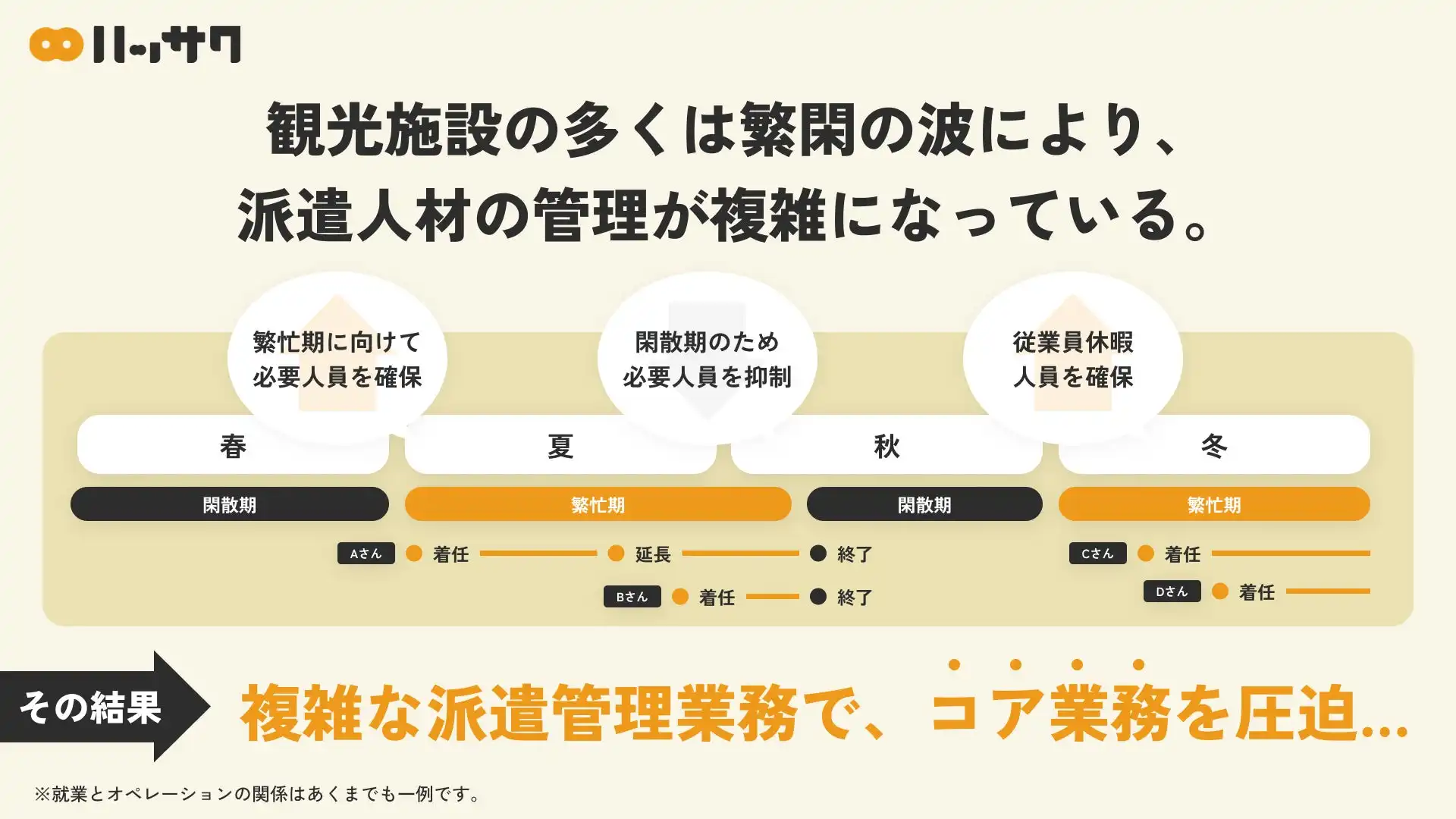営業妨害とは
営業妨害とは、他者の経済活動を不当に妨害する行為を指します。具体的には、虚偽の情報の流布や、物理的な妨害、信用毀損などが該当し、これらの行為は、公正な競争を阻害し、被害者に経済的な損害を与える可能性があります。営業妨害は、法的な責任を問われるだけでなく、企業の評判を著しく低下させる原因にもなり得るため、企業は適切な対策を講じる必要が生じます。
営業妨害は、不正競争防止法や刑法によって規制されており、違反した場合には、損害賠償請求や刑事罰が科されることがあります。例えば、競合他社の製品に関する虚偽の情報を意図的に流布し、その結果、売上が減少した場合、損害賠償責任を負う可能性があります。また、店舗の前で騒ぎを起こしたり、客を脅したりするなどの物理的な妨害行為も、営業妨害として法的措置の対象となるでしょう。
企業が営業妨害を受けた場合、まず証拠を収集し、法的措置を検討することが重要です。証拠としては、誹謗中傷の書き込み、業務妨害の記録、売上減少のデータなどが挙げられます。弁護士に相談し、法的手段を通じて損害賠償を請求したり、差止請求を行うことが考えられます。また、警察に被害届を提出することも、状況によっては有効な手段となります。
営業妨害への対策
「営業妨害への対策」に関して、以下を解説していきます。
- 風評被害対策
- 従業員の教育
風評被害対策
風評被害対策は、インターネット上や口コミで広がるネガティブな情報から企業を守るために不可欠です。企業イメージを損なう可能性のある情報に対して、迅速かつ適切に対応することで、被害の拡大を最小限に抑えることが重要になります。
具体的な対策としては、ソーシャルメディアモニタリングの実施や、検索エンジンの評判管理、そして顧客との積極的なコミュニケーションが挙げられます。これらの対策を通じて、企業は自社の評判を積極的に管理し、風評被害のリスクを軽減できます。
| 対策 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| モニタリング | SNSの監視 | 早期発見 |
| 評判管理 | 検索結果の最適化 | 悪評の抑制 |
| コミュニケーション | 顧客との対話 | 信頼関係の構築 |
| 情報発信 | 正確な情報提供 | 誤解の解消 |
従業員の教育
従業員の教育は、営業妨害を未然に防ぐための重要な取り組みであり、コンプライアンス意識の向上と適切な行動規範の周知が不可欠です。従業員一人ひとりが企業の代表として、倫理観を持って行動することで、企業全体の信頼性を高めることができます。
教育プログラムでは、不正競争防止法や個人情報保護法などの関連法規に関する知識だけでなく、SNS利用時の注意点や顧客対応における適切な言動についても学ぶ必要があります。定期的な研修やeラーニングを通じて、従業員の意識向上を図ることが重要です。
| 教育内容 | 目的 | 方法 |
|---|---|---|
| 法令遵守 | 法規制の理解 | 研修の実施 |
| SNS利用 | 炎上対策 | ガイドライン策定 |
| 顧客対応 | 信頼獲得 | ロールプレイング |
| 情報管理 | 情報漏洩防止 | セキュリティ教育 |